陸自第15旅団「辞世の句」再掲載の背景―自衛隊の大東亜戦争史観を支える防研『戦史叢書』―
- 軍事問題研究会編集
- 2025年1月26日
- 読了時間: 7分
更新日:2025年1月30日
『軍事民論』第746号(2025年1月28日発行)…5頁
陸自第15旅団「辞世の句」再掲載の背景
―自衛隊の大東亜戦争史観を支える防研『戦史叢書』―
陸上自衛隊第15旅団(那覇)は1月1日、牛島 満 日本軍第32軍司令官の辞世の句を公式HPに再び掲載した(YAHOO!ニュース)。
同司令官の辞世の句は、地元メディアの報道をきっかけに一部の市民団体などから批判が出たことで同旅団が昨年(2024年)10月末に一旦取り下げていたが、HPリニューアルを口実に復活させたものだ。
昨年は幹部自衛官の靖国神社参拝や、第32普通科連隊が公式アカウントに「大東亜戦争」との呼称、陸自幹部候補生学校の沖縄戦史現地教育実施計画に「日本軍が善戦敢闘」との記述など旧軍と自衛隊との関わりを巡り物議を醸す問題が起きた。

これら問題に対する想定問答を陸幕監理部総務課が「政教分離・歴史観関連」*1(以下『想定問答』)と題してまとめている。内容から、陸上幕僚長が定例記者会見での質問に答える際の答弁ラインを設定したものと思われる。
本号では『想定問答』から特に重要部分を抜粋・紹介したい。
この『想定問答』を読んで、昨年の一連の問題の根底には自衛隊における大東亜戦争史観があると理解できた。そしてその基となっているのが『戦史叢書』の存在だ。
同書は、防衛省・自衛隊のシンクタンクである防衛研究所の前身である防衛研修所が「自衛隊の教育又は研究の資とすることを主目的として」*21966年から1980年にかけて全102巻刊行したものだ。実際、『想定問答』(25頁)は沖縄戦史現地教育実施計画に「善戦敢闘」と記載された根拠を「戦史叢書 沖縄方面陸軍作戦」としている。

同書が編纂された当時の関係者の動機は「敗戦後の混乱から徐々に冷静さを取り戻し始めた頃、旧陸海軍関係者などの中から、戦争という歴史的事実を後世に伝えるために、大東亜戦争史を編纂すべきであるとの声が高ま」*3ったことにあった。そして延べ100人以上にのぼる同書の編纂官及び調査官の「ほとんどが戦争経験者」*4であったことから大東亜戦争肯定論(「大東亜戦争史観」)から逃れることができなかったのである。
こうした背景から編纂された同書は、「(原稿の)執筆完了後、戦史室内で詳細に審議して防衛研修所に持ち込み、副所長以下の陸海空所員による審査を受けた。しかし、これら審議、審査の全過程に於いて、旧軍時代の陸海軍対立の残滓が依然として存在し*5、それぞれの立場を擁護しようとする空気が濃厚であった。その結果、一部、史実の省略や削除、文章表現の変更等を余儀なくされ、執筆者としては納得出来ない点も少なくなかった」*6まま刊行されたのである。
またこの他にも同書の最も特異な点は、開戦経緯が陸海二本立てとなっていることがある。これは、「まずは陸海軍のそれぞれの関係者(ステーク・ホルダー)に理解を求めるという観点が優先されていたことを物語っている」*7との指摘がある。「関係者(ステーク・ホルダー)に理解を求める」という言い回しは、旧軍時代に後輩であった編纂官らが先輩達に遠慮して旧軍に対する批判的な記述を遠慮したことを遠回しに述べているのだ。
これらについて筆者も思い当たることがある。30年以上前にある戦史の研究会で「戦史叢書はウソばかり書いてある」という論難に対して、編纂官を務めた方が「当時はまだ生きている人がいて本当のことが書けなかった」と悲痛な表情で弁解していたことを覚えている。
既に『戦史叢書』は、「新たな史料も発掘され、史実の間違いも散見されるようになった。この際、改めて史実を精査し、過去のしがらみや特定の史観に捉われることなく、真に正鵠な戦史が書かれることを念願して止まない」*8という評価が当時の編纂官から下されており、今日的には史実に耐えられない書物なのである。
同書を正史として歴史認識が形成されている限り、自衛隊は今後とも同様な問題を繰り返すであろう*9。
(脚注)
*1 (資料番号:25.1.16-1)「政教分離・歴史観関連」(文書管理者:陸上幕僚監部監理部総務課長 作成年月日:6.7.25)。なお資料番号とは資料の整理・保存のために本会が便宜上付けた番号である。
*2 (資料番号:25.1.14-1)「『戦史叢書』刊行30周年に寄せて」『戦史研究年報』(防衛研究所)第13号(2010年3月31日)81頁。
*3 (資料番号:25.1.14-2)「『戦史叢書』の来歴および概要」『防衛研究所戦史部年報』(防衛研究所)創刊号(1998年3月)70頁。
*4 (資料番号:25.1.14-1):81頁。
*5 藤井 治夫「自衛隊―この戦力」(三一書房 1970年12月15日 第1版第1刷発行)によると1968年当時、自衛隊の幹部のうち13.8%を旧軍人が占めており、その内訳は将クラス80%、1佐78%、2佐66%、3佐21%(227頁)。
*6 (資料番号:25.1.14-3)「『戦史叢書』編さん当時の思い出」『戦史研究年報』第13号84頁。
*7 (資料番号:25.1.14-4)「市ヶ谷台の戦史部と戦史叢書」『戦史研究年報』第13号93頁。
*8 (資料番号:25.1.14-3)84頁。
*9 大東亜戦争史観が自衛隊に与えている影響については、「陸上自衛隊の部隊がXで「大東亜戦争」と表現した背景~「商業右翼」が自衛隊教育に影響か?~」が参考となる。
〔解説〕桜井 宏之(さくらい・ひろゆき/本会代表)
(掲載項目)*問いは連番だが、本号ではそこから抜粋している。
問2: 32i(編集部注:32普通科連隊のこと)の公式SNSや1月の陸幕副長らによる靖国神社参拝に係る行政文書において「大東亜戦争」という呼称が使用され、福岡市の護国神社での特攻隊慰霊行事における音楽演奏において軍歌が演奏されるなど、先の大戦を美化する歴史観の保持や旧日本軍と決別できていない状況を疑われる事案が発生しているが、陸幕長の見解如何
更問:大東亜戦争の呼称使用
15旅団HPへの牛島司令官辞世の句掲載
問3: 先の大戦を美化する歴史観の保持や旧日本軍と決別できていない状況を疑われる事案が発生しているが、陸自における歴史教育の状況如何
更問:幹部候補生学校での沖縄戦史現地教育において、沖縄戦では旧日本軍が長期にわたり善戦したとの評価に基づき、戦闘に焦点を当てた教育を実施し、住民避難の状況など住民目線の教育を実施していないとの指摘があるなど、偏った歴史教育を実施しているのではないかと問われた場合
更問:沖縄戦史現地教育の実施計画に記載に(原文ママ)ある日本軍が善戦敢闘したとの記載について改める考えはないのかと問われた場合
問4: 沖縄県の市民団体が15旅団HPに掲載された牛島司令官辞世の句などを全文削除するよう要求しているが、現在の対応状況如何
更問:旅団の沿革に牛島司令官の辞世の句を掲載していることは、15旅団が32軍との連続性を意識している表れではないかと問われた場合
更問:旅団の沿革に掲載されている牛島司令官の辞世の句に対して、臨時第1混成群の初代群長が強い思いを持っていたとのことであるが、旅団の公式HPに個人の思いを掲載することは問題ないのかと問われた場合
更問:掲載されている辞世の句を削除する考えはないのかと問われた場合
更問:15旅団における具体的な対応状況について問われた場合
更問:6月6日の陸幕長会見で、「削除を検討する」旨発言しているが、陸幕としては何も指示や検討はしていないということか
【関連情報】
「大東亜戦争」は自衛隊の公式用語 *ここをクリック
防衛省HPに掲載されている「大東亜戦争」*ここをクリック
(以上、いずれも全文を知りたい方は本会までお問い合わせ下さい)
問題となっても「大東亜戦争」はやめられない *ここをクリック
日本軍、沖縄戦で「長期にわたり善戦敢闘」―陸自沖縄戦史現地教育 *ここをクリック
部内教育資料から見た自衛隊精神教育 *ここをクリック
爆撃機の損失率を比較対照すると「面白い」―防研部内研究 *ここをクリック
□ 頒価 ¥300円(前金制)
下記本会口座までご入金戴くと共に、本会アドレス(ttn5rhg28d@mx2.ttcn.ne.jp)まで「『軍事民論』第746号注文」とお申し付け下さい。
お振込み確認後、PDFファイルをメールにて送付致します。
□ 領収証
発行しませんのでご注意下さい。
ただし本誌又は本会ニュースのバックナンバーを合わせて¥500円以上をご購入の場合は、お申し付け戴ければ発行致します。
(振込先:郵便振替)
【郵便局でのお振込みの場合】
口座番号:00110-1-44399
加入者名:軍事問題研究会
【銀行またはインターネット・バンキングでのお振込みの場合】
銀行名:ゆうちょ銀行
金融機関コード:9900
店番:019
預金種目:当座
店名:〇一九店(ゼロイチキユウ店)
口座番号:0044399
加入者名:軍事問題研究会
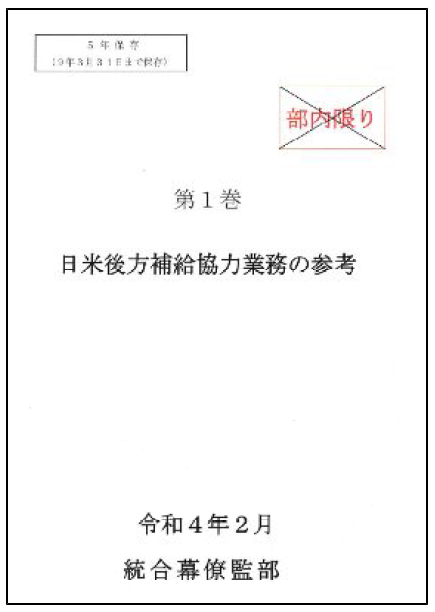


コメント