自衛隊における「戦域」とは・・・「一つの戦域」構想が意味すること
- 軍事問題研究会編集
- 2025年4月16日
- 読了時間: 3分
中谷 防衛相が3月末のヘグセス米国防長官との会談で、中国への対抗を念頭に、東シナ海や南シナ海、朝鮮半島を中心とした地域を一体の「戦域」としてとらえ、日米が同志国とともに防衛協力を強化する「ワンシアター(一つの戦域)」構想を伝えていたと報じられている(『朝日新聞』)。
「戦域」について自衛隊ではどのように定義されているか、そしてこの発言の意味するところを紹介したい。
「自衛隊の統合運用に関する教育訓練の資とするため、自衛隊の統合運用に関し、使用する用語の意義を明らかにすることを目的」(「前文」)に作成された「統合用語集」(統合訓練資料1-5)は、「戦域」を以下の通り定義している。

出典から分かる通り、自衛隊の「戦域」の概念は米軍からの借り物なのである。
ただし「日米後方補給業務に関する主要な用語の意義を明らかにして、業務処理上での参考に資するために作成」(「はしがき」)された「日米共通用語集(後方補給編)」(2007年3月 統合幕僚監部首席後方補給官)では、「戦域間輸送」という用語が以下の通り定義されており、「戦域」に関して日米間で概念を共有していることが分かる。

記事では「ワンシアターの明確な地理的範囲は決まっておらず」とあるが、明確な地理的限界が設けられることはなかろう。なぜなら「戦域」の定義にある通り、「作戦部隊に割り当てられる区域」なので、作戦規模に応じていくらでも拡大するのである。敢えて限界を設けるとすれば、米インド太平洋軍の責任区域(Area of Responsibility)ということになろうか。
そうなる理由は、米統合参謀本部教範「Joint Campaigns and Operations」(Joint Publication 3-0)から理解することができる。
まず米統合軍司令官には責任区域が与えられ、この中にarea of operation(陸上又は海上部隊の司令官が任務を遂行し、自軍を保護するために定める作戦区域)やtheater of operation(特定の軍事作戦の実施又は支援のために戦闘指揮官が定めた作戦区域)が設けられるからである。

なお東シナ海や南シナ海、朝鮮半島を中心とした地域を一体の「戦域」という構想は、米シンクタンク「戦略予算評価センター」(CSBA)がまとめた報告書「BEYOND PRECISION: MAINTAINING AMERICA'S STRIKE ADVANTAGE IN GREAT POWER CONFLICT」が示す台湾有事シナリオと見事に合致する。中谷 発言が台湾有事を念頭に置いてこの発言を行ったことは間違いないであろう。
下図は同報告書に掲載された、台湾への大規模な着上陸を阻止するため、台湾海峡における中国軍の侵攻部隊を迅速に無力化するシナリオにおける作戦範囲―戦域と理解して良かろう―である。

なおこの図のシナリオでは自衛隊は参戦していない。こうした事態に自衛隊がどのように絡むかの一端を「米第7艦隊の指示で陸自地対艦ミサイルが発射される」(本誌第735号)で紹介しているので一読されたい。
【関連情報】
4月月例研究会
「台湾有事に必要な弾薬量」
*ここをクリック
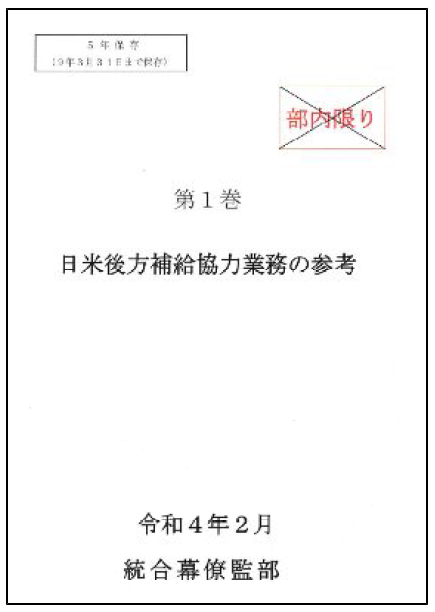

コメント